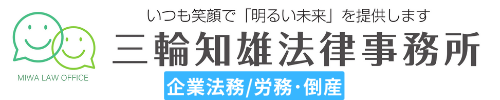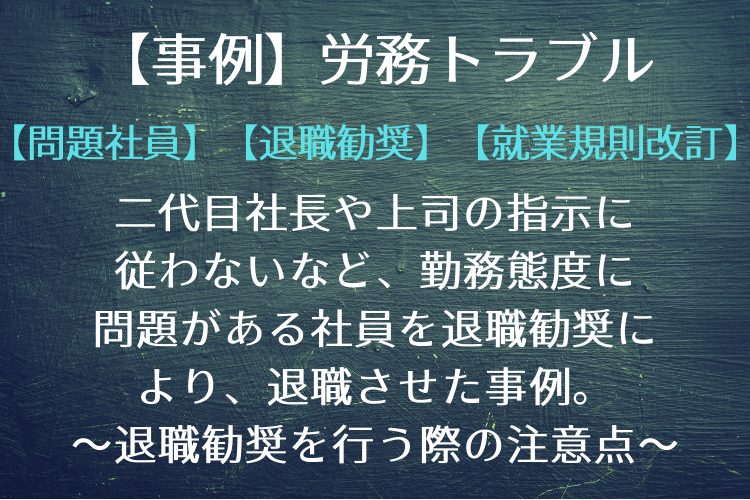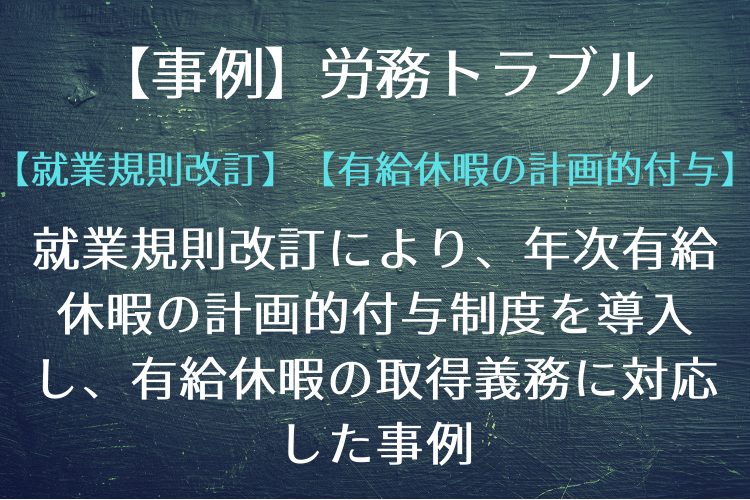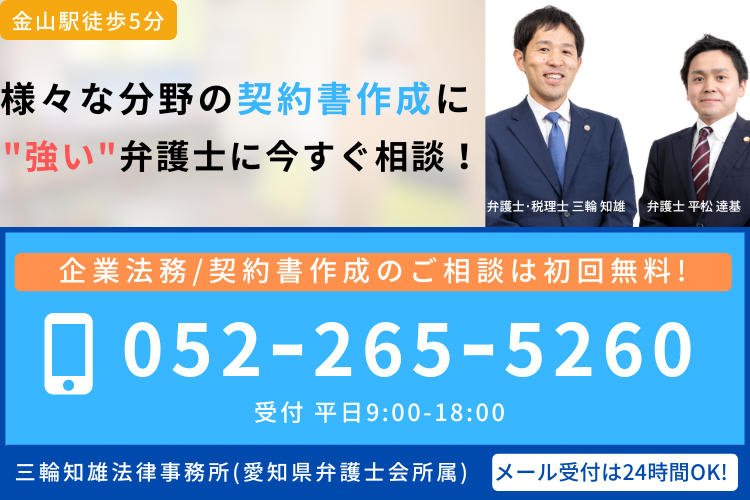ご相談メニュー
- 取引基本契約書作成のご相談
- トラブル解決や事業提携の開始・終了に伴う合意書、示談書、和解書等の作成のご相談
- 売買契約書作成のご相談
- 工事請負契約書作成のご相談
- 特定商取引法の契約書作成のご相談
- 就業規則・雇用契約書作成のご相談
- 事業譲渡契約書作成のご相談
よくあるご相談例
「口頭での契約や、注文書・請書での合意も契約として有効ですか」とご相談を頂くことがあります。
口頭での契約や、注文書・請書などによる簡易な合意も、契約としては一応有効です。
しかし、契約書を作成していなかったり、簡易な条項しかない場合は、どうしても契約内容があいまいとなってしまうため、相手方から、「そんな約束はしていない」、「その金額は追加工事を含んだ金額だ」、「支払条件が違う」など様々なクレームを受けたり、結果的に代金を請求することができないなどのトラブルに巻き込まれる危険が高まります。
したがって、契約書の作成にあたっては、契約ごとに将来発生しうるトラブルを予想し、会社の利益を守るために必要な条項があるかを弁護士がチェックし、条項が不足している場合には、それを補充した契約書の作成が必要です。
以下、問題となる契約の類型ごとにご説明いたします。
三輪知雄法律事務所の契約書作成・リーガルチェックサービス
1.取引基本契約書作成のご相談
取引基本契約書とは、特定の取引先との取引について、基本的な項目を定める契約書です。取引基本契約書は、会社の取引の基本的な事項を定める契約書であるため、多くの取引に用いられます。
しかし、当事務所の法律相談では、安易にひな形に頼って取引基本契約書を作成し、取引の実態をふまえない内容となっている取引基本契約書を多く目にします。
取引基本契約書は、会社の商流、扱っている商品の特性、売上が入金されるタイミングなどの個別事情をふまえ、自社の有利・不利を十分に検討したうえで作成する必要があるため、担当弁護士が、会社の商品の特性や取引の実態をしっかりとお聞きして、どんな条項が必要か検討・アドバイスを行い、“いざという時に強い”取引基本契約書を作成いたします。
2.トラブル解決に伴う合意書、示談書、和解書等の作成
トラブル解決の際の示談書・和解書や、事業提携の開始・終了の際の合意書などについては、トラブルの内容や合意・解決条件等により、条項は千差万別です。
合意書・示談書は、解決内容として、いつまでに支払、いつまでに何の行為を行うか、どのようにしてその行為が行われたことを確認するか、物の受け渡しはどのように行うかなど、全ての解決条件を法的に意味のある条項として網羅し記載しておかなければなりません。
また、法律面はさることながら、税務面、引換えに給付する物の受領や完了の確認においても問題がない合意条項を準備する必要があります。
この種の書面は、合意書、示談書、和解書、解決書、覚書、念書など色々な文書名がありますが、文書名が与えるイメージは重要ですので、トラブルの内容や性質にしたがった適切な文書名を設定します。
一例として、「示談書」という文書名は、トラブルや紛争の解決で金銭支払を伴う場合に使われることが多いです。
また、顧客とのトラブルやクレームの解決時の書面は「示談書」でも良いですが、将来的な解決指向の意味を込めて、「合意書」、「和解書」としても良いでしょう。
なお、昨今では、SNSを通じてネット上で拡散されるのを防ぐため、トラブル解決の際には、解決内容について、第三者への伝達やSNSへの書き込みは行わないというような非開示条項の設定についても検討を要すると考えられます。
会社の”いざ”を想定して、どんな条項が必要か検討・アドバイスを行い、“いざという問題が起こっても強い”、合意書・示談書・和解書などの文書を作成いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
3.売買契約書作成のご相談
売買契約書は、売主にとっては代金確保のための重要な書類となります。
トラブル時にも、適法に代金回収ができるようにしておく必要がありますし、商品の納入、検収、検査方法や代金回収までの期間などについて定めておく必要があります。
他方、買主の立場からは、契約不適合責任(改正前民法の瑕疵担保責任)や、不測の事態が発生した場合の処理などについて条項を整備しておく必要があります。
輸入品による供給が主体となる商品については、昨今の国際情勢の不安定さをふまえますと、緊急の場合の対処方法を定めた条項(具体的には、国内品購入の対応等)を定めておく必要があると思われます。
また、商品の特性上、最終消費者が購入して実際に使用してからでないと、商品の不備が分からない商品もあります。
そのような商品の特徴や、取引の特性を十分考慮したうえで、検査体制や契約不適合責任の条項を設定しておかないと、売買契約成立後に予想外の不利益を受ける危険があります。
当事務所では、相談者様の契約書にどんな条項が必要か検討・アドバイスを行い、“いざという時に強い”売買契約書の作成いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
4.工事請負契約書作成のご相談
工事請負契約書は、三輪知雄法律事務所におけるご相談でも、現実には意外と作成されていない契約書の一つです。
建設工事、建築工事、土木工事業などでは、業界的に見積書と請書で対応することが多いという、業界の慣習に原因があるのかもしれません。
しかし、工事請負契約では、本来、何の工事をいつまでにすべきか、債務の内容を明確にし、万一、第三者に損害が発生してしまった場合に誰がどのように対応するかなど、実は、事前に取り決めておくべき事項は多くあります。
実務上、工事請負契約で多く発生するトラブルとしては、工事の途中解約のトラブル、下請業者が工事完成前に連絡が取れなくなったというトラブル、工事後のミスや追加工事代金をめぐるトラブルが多く発生しています。
また、工事請負契約に追加工事はつきものですので、追加工事に関する工事範囲や責任範囲、万一、下請業者が、第三者に損害を発生させた場合に、誰がどのような方法により対処するのかも決めておく必要があります。
三輪知雄法律事務所では、担当弁護士が、相談者様の会社の工事請負の特性や取引の実態を、しっかりとお聞きします。
そして、相談者様の契約書にどんな条項が必要か検討・アドバイスを行い、”いざという時に強い”工事請負契約書の作成をいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
▼工事請負契約書作成に関する参考事例はこちら▼
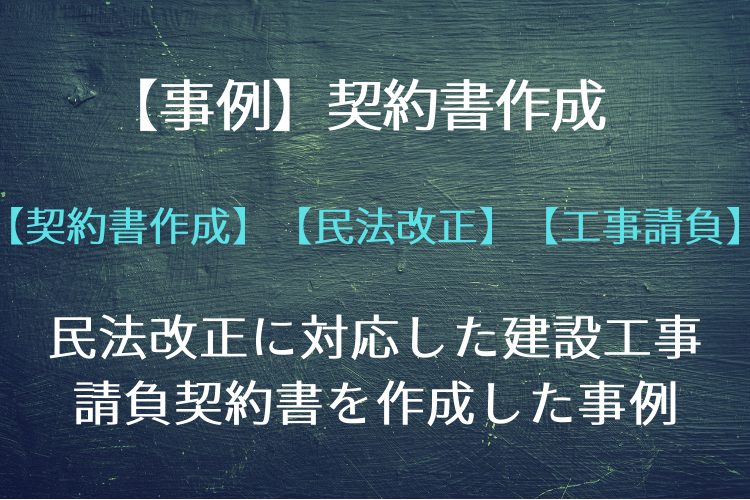
5.特定商取引法の契約書作成のご相談
特定商取引法は、特定の商取引を行う事業者に対する規制を定めた法律です。
特定商取引法において、最も重要で注意しなければならない規制は、クーリングオフ制度(※)です。
※クーリングオフ制度:契約書面の受領から8日の間は、購入者は、事業者側の落ち度その他理由を問わず自由に解約できる制度です。
このクーリングオフ期間の8日間は、法律が定める記載事項が記載された契約書を、購入者に交付したときからスタートしますので、契約書に特定商取引法の要件を満たさない不備があると、いつまでたってもクーリングオフ期間の8日間がスタートしません。
結果として、8日間どころか何ヶ月もの時間が経過したにもかかわらず、自由に解約(クーリングオフ)されてしまう恐れがあるということになり、事業者は、受取った購入代金を原則として全額返還しなければなりません。解約不可という条項があっても同様です。
したがいまして、特定商取引法に該当するサービス提供を行う事業者においては、特定商取引法の要件を満たす契約書を使用することが非常に重要となります。
また、特定商取引法では、勧誘や広告に関してもたくさんの行為規制があります。
営業方法や解約の受付対応に問題があるなど、特定商取引法に違反する状態が繰り返されるなど、違反が悪質と見なされた場合には、都道府県、経済産業局及び消費者庁などから、立ち入り検査を受けることがあります。
違反の程度によっては、監督官庁から業務停止命令を下されるなど、事業者にとっては、取り返しのつかないダメージを受けることがありますので、特定商取引法における規制を軽視してはなりません。
三輪知雄法律事務所では、担当弁護士が、相談者様の会社の商品やサービスの内容、特性、取引の実態などをしっかりお聞きし、”いざという時に強い”特定商取引法の要件を満たす契約書を作成いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
▼特定商取引法に関する契約書作成の参考事例はこちら▼
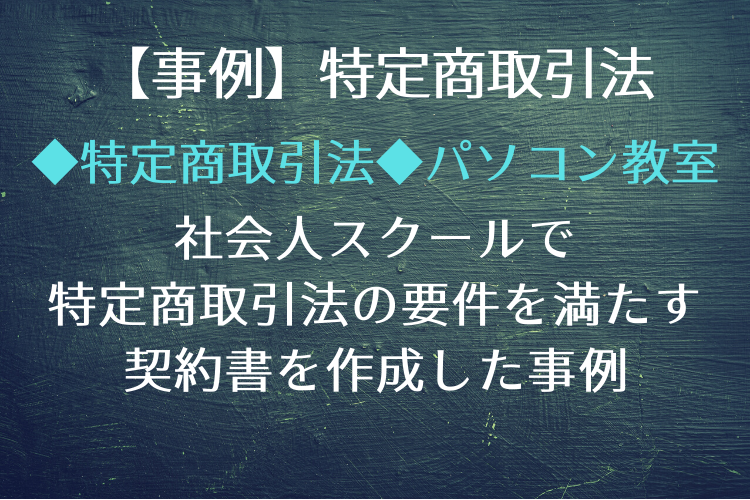
6.就業規則・雇用契約書作成のご相談
就業規則は、会社や従業員が守るべき労務に関する重要なルールを定めるもので、常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則を作成し、労基署に届け出る義務が課せられています。
雇用契約書とは、雇用主と使用者間で、労働条件や雇用の際に遵守すべき事項についてとりかわす契約書です。
現実には、”とりあえず”就業規則を作成し、労基署に提出している会社や、具体的な業務内容や指示内容が一切文書やメールに残らず、雇用契約書も通り一遍の労働条件だけを記載して作成している会社が多いのが実情です。
現実の労働審判や裁判等において、就業規則や雇用契約書の条項や記載について、裁判官から会社側の主張が否定されるなど、実際の労務トラブルで通用せず、予想外の損害を被るケースも見受けられました。
雇用契約書も、労働条件などを記載した通り一遍のものではなく、就労に際しての基本的な注意義務、業務指示について明示しておく必要がある事項、場合によっては、過去の労務トラブルをふまえた特記事項も必要と思われます。特に、雇用契約書は、就業規則を作成していない会社では、唯一の明文で労働条件や雇用における注意義務を定める重要な文書となりますので、きちんと検討して作成すべきです。
就業規則についても、法改正、会社の社員構成、賃金体系等の変化に応じて適宜変更が必要であり、労務トラブルの際にも通用する内容であることが当然要求されます。このような観点から、当事務所では、就業規則の改訂、届出にも対応しております。
▼就業規則改訂に関する解決事例・参考事例はこちら▼
7.事業譲渡契約書、株式譲渡契約書のご相談
会社の事業の一部、または全部を譲渡する際に事業譲渡契約書が作成されたり、事業承継やM&Aの際に株式譲渡契約書として作成されることも増えております。
事業譲渡契約書は、対象となる資産、負債、顧客や営業先についても、地域などで範囲が設定できる場合には、明示しておく必要があります。
また、事業譲渡に伴う、競業避止義務の内容、事業名称の変更や商標権の問題など、きちんと取り決めておかなければならない内容をきちんと網羅しておくことが必要になります。
また、M&Aの際に締結される株式譲渡契約書については、法務DD(デューデリジェンス)後に顕在化した法的リスクに対処するための条項を取り入れた株式譲渡契約書を作成いたします。
事業譲渡契約や株式譲渡契約書においてトラブルが発生すると、事業の譲渡が不完全になったり、譲渡代金の返還請求を受けるなど双方が弁護士を立てて争う問題が発生するリスクが大です。
当事務所では、事業譲渡やM&Aに伴う株式譲渡のご相談に際し、いざという時に問題が発生しないように、事業譲渡契約書や株式譲渡契約書の作成・リーガルチェックに対応しております。
契約書作成・リーガルチェックのご相談はこちらから
三輪知雄法律事務所の「契約書作成やリーガルチェックに強い弁護士」へのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、画像をクリック頂き、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※本記事は公開時点の法令及び当事務所のこれまでの取扱事例を下に作成しております。